抱っこ遊びで心と体を育てる
特性にもよりますが、抱っこが好きな子は多いです。
実は「抱っこ」は乳幼児期の子どもの心と体に非常に大切なことです。
1.心を落ち着け、愛着を形成する
2.前庭感覚、体性感覚、視覚を刺激して運動機能向上に関連
抱っこの心への効果
悲しい時、痛いとき、子どもたちはよく抱っこを求めます。
そして抱っこをすることで落ち着きを取り戻します。
これは、抱っこをすることで分泌されるホルモンが関係していると言われています。
幸せホルモンのセロトニン、愛情ホルモンのオキシトシンが分泌されることで気分を落ち着ける効果があります。
子どもたちは様々な困難に直面しても、抱っこで心を落ち着け、乗り越えていきます。
また、発育発達は親子の愛着形成をベースとしています。
抱っこを通じたオキシトシン分泌は発育発達の根っこになります。
抱っこの体への効果
抱っこをすることは体にも良い影響を及ぼします。
いわゆる「運動神経」「ボディイメージ」といった運動能力に関係する機能に「体性感覚」「前庭感覚」「視覚」があります。
体性感覚は「自分の体を触れられている」「物が体に触れている」「触っている」といった感覚です。
抱っこでギューっとしてあげることで、強い刺激が入り、体性感覚が鍛えられていきます。
前庭感覚は「体が左右に動いている」「上下に動いている」「スピードが速い、遅い」「バランスを取る」といった機能です。
抱っこで子どもを振る向きやスピードに関係します。
もう一つ、視覚も鍛えることができます。
ここでいう視覚は視力のことではなく、物との距離感や視野の広さのことです。
抱っこをしている時の視線をどれだけ動かしてあげられるかが関係します。
発達に不安のある子たちは
・ボディイメージが弱く、よく人や物にぶつかる
・運動がぎこちない
といった特徴があります。
こういった運動機能の根底にあるのが、体性感覚、前庭感覚、視覚です。
それぞれの感覚を刺激していくことで、脳の新しい神経回路が作られて発達が進みます。
抱っこをすることがこれらを鍛えることができるのですが、、、、
ちょっとしたコツがあります。
それが抱っこ遊びです。
運動機能を高める抱っこ遊びのコツ
ただ抱っこをするだけでなく、そこから遊びに繋げます。
運動機能を高くするための抱っこ遊びのコツは、4つ。
1.いろんな強さで体性感覚を刺激(優しいギューから強いギューまで)
2.子どもをいろんな方向へ持ち上げて前庭感覚と視覚を刺激(上下左右、斜め上、斜め下、左右回転)
3.子どもの向きを変えて前庭感覚と視覚を刺激(親の方を向く、親と反対を向く)
4.組み合わせる
*いずれも安全を考慮したうえで実施してください
*首の座っていない乳児には大きな刺激を与えない様に注意してください。
抱っこ遊びでこれらの感覚を刺激してあげることで、新しく脳の神経回路を作ることに繋がります。
泣いている時などに無理して行う必要はありません。
泣きたいとき、つらいときは落ち着くまで優しく抱っこしてあげて下さい。
愛着形成をしながら、運動機能にも必要な刺激の入る抱っこ遊び、ぜひやってみて下さい。
スパーク西京極では、、、
スパーク西京極でも抱っこはたくさん行っています。
子どもたちを褒める時、共感して寄り添う時はもちろん、抱っこ遊びもしています。
スタッフとの関係性構築や、感覚を刺激する遊びとして抱っこは大変効果的だと感じています。
遊びを繰り返す大切さ
勉強やスポーツでは「繰り返すこと」がとても大切にされています。
それは遊びでも同じで「繰り返すこと」には、心にも体にも重要な意味があります。
遊びは子どもたちにとって他者とのかかわりや感情の調整を学ぶ場であり、脳と体の機能を育む場です。
一度しただけでは不十分で、繰り返し取り組むことで心と体に定着していきます。
運動は脳の神経の繋がりを強くする
スパークは「運動」を基本とした遊びを行っています。
運動には様々な種類があります。
・有酸素運動(血流を増加させて頭がよく働く。ホルモンが出て気分が落ち着く。神経細胞を増やす物質も出る)
・粗大運動(ジャンプやかけっこ等、筋力や感覚の基礎を養う)
・協調運動(2つ以上の動作を同時に行い、動きを協調させる:縄跳びなど)
・コントロールの運動(ボール投げ等、体の動きを調整する運動)
・微細運動(字を書いたり、お箸をもったりすることに繋がる細かい指先の運動)
こういった運動をすることで脳の神経細胞が発達し、情動や体をコントロールする力がついていきます。
加えて筋力や心肺機能も向上していきます。
ところが、こういった運動(遊び)は1回だけでは効果が無く、何度も、何日も繰り返していくことで効果を発揮します。
勉強やスポーツも繰り返すことで上達したり覚えたりします。
これも、脳の神経細胞が発達していくからこそです。
遊びも同じで、遊びの中で何度も繰り返して体を使うことで脳が発達していきます。
他者との関わりを学ぶ
遊びは体を動かすことだけが目的ではなく、遊びの中で他者と関わり、コミュニケーションを取る能力を身に付けるという目的もあります。
コミュニケーションも練習です。
1回だけではなかなか身に付きません。
繰り返すこと、すなわち遊んでたくさん他者と関わることで養われます。
発達に特性のある子たちは、特性ゆえにその機会が少なくなってしまったり、関わり方を学ぶことが難しかったりします。
そこで、スパーク西京極では必ずお子様1人に対して1人の療育スタッフが担当して、何度も何度も関わって、コミュニケーションの練習を促しています。
遊びに意味を見出す
遊びに対して意味を見出すためにも繰り返しが重要です。
子どもが行った何気ない行動も、大人が「それ面白いね」と言って拾ってあげることで
何気ない行動に意味が生まれます。
行動に意味が生まれると遊びになります。
遊びになるとコミュニケーションへとつながっていきます。
繰り返して遊ぶうちに意味が定着し、「こうやって遊ぶんだ」と子どもたちがは学び、他者と関われる機会を増やしていきます。
時々余裕がある時だけで良いので、
お子様が何気なく投げたボール、何気なくジャンプした、走った
いろいろな行動にアンテナを張ってみてください。
遊びは身近にあふれています。
園との連携を取っています
先日、スパーク西京極の職員で施設利用者様が通われている幼稚園を訪問させていただきました。
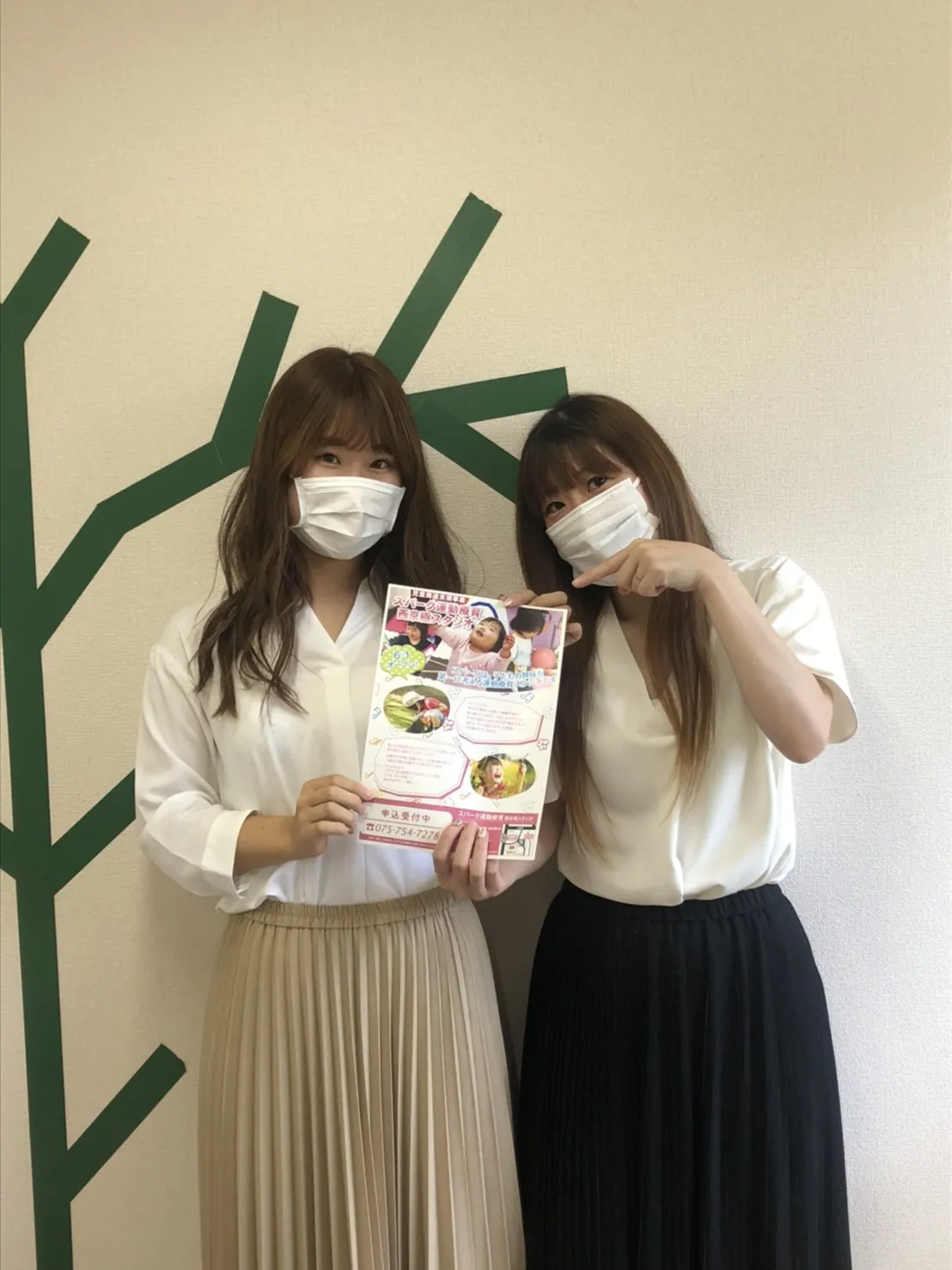
スパーク西京極では以前から必要に応じて幼稚園・保育園との連携を取っています。
こちらから園を訪問してお子様たちの普段の様子を見たり、園の先生方にスパークでの様子を見に来ていただいたりしています。
園との連携の際には、先生方との話し合いの時間も確保し、お子様一人一人の現在の課題や支援の方向性について共有しています。
園での様子を見ておくことで、普段スパークでは見られない子どもたちんの様子を知ることができます。
その中で、新しく長所を見つけることができたり、療育で支援していくべき課題が明らかになったりします。
園との連携で得た情報は、その後スタッフ間で共有し、その後の療育に役立てています。
今後も必要に応じて順次園訪問を行っていく予定です。
子どもの遊びを深めてあげよう
スパーク西京極の療育スタッフたちは、日々子どもたちの遊びの内容を複数の要素に分けて観察しています。
遊びの内容はある程度発達の段階とリンクしており、遊びを発展させていくことが発達にも繋がっていくと考えています。
ご家庭でお子様と遊ぶ時に今回ご紹介するような視点を持っていただけると、お子様との関わり方が少しわかりやすくなるかと思います。
遊びにおける興味の数、時間、深さ
【数】どれほど多くの種類の遊びに興味を持つか
【時間】1つの遊びに対する時間はどの程度か
【深さ】遊びは深まっていくか
こういったことをスタッフたちは見ています。
いずれも、多ければ良くて、少ないから悪いという意味ではありません。
例1)数は多いけれど、、、
例えば、ADHDと診断されていて、集中力や落ち着きが無い子。
遊びの数は多いけれど、1つ1つの時間は短く、深さもないという場合。
そういった場合、スタッフたちは1つ1つの遊びに様々なバリエーションを付けたり、興味が長続きするように面白おかしく関わったりして、時間と深さを伸ばすようなかかわりをしています。
面白おかしく関わることはなかなか難しいかもしれませんが、バリエーションを増やしてあげることは比較的しやすいかと思います。
例えばお家でよく子どもがしがちな、ソファーから跳ぶという遊びだと、以下のようなバリエーションがあります。
(ソファーから跳ぶことをお勧めしているわけではないので、禁止されているご家庭では他の遊びで考えてみて下さい。あくまでも例です。)
・跳ぶ目的地を決めてみる(クッションを飛び越える、クッションの上に立つ など)
・目的地の場所を変える(遠くしたり、近くしたり、右にしたり左にしたり)
・跳び方を変える(後ろ向き、片足、バンザイ、動物やヒーローのポーズ など)
・高さを変える(ジャンプで大人の手をタッチなど)
これだけでも跳ぶという遊びの中でバリエーションが10個近くに増えました。
この様に、遊びの刺激を変えてバリエーションを増やすことで、1つの遊びへの集中力を養ったり、「次はどうしようか」と考え、遊びを深めていく力を養っていくことができます。
また、大人から「こうやって深めるんだよ」という提示にもなり、子どもたちはそれを学んでいきます。
例2)遊びの時間は長いけど
遊びの時間は長いけれど、興味の数が極端に少なく同じ遊び、動きばかりしている場合。
数と深さが少ないと判断できます。
そういった場合は、興味を持ってもらえるかどうかは分からないけれど、たくさんの遊びをこちらが提示してあげるという関わり方をしています。
空振りを恐れず、いろいろと提示しています。
その中で1つでも興味を持ってもらえれば、世界は広がります。
また、同じ遊びの中でも例1)のように、バリエーションをたくさん示してあげることも効果的です。
何に興味を持つかということについては、ある程度「数うちゃ当たる」という割り切る気持ちも大切です。
興味の数が少ない子には大人が楽しく遊んでいる姿をたくさん見せて、刺激をたくさん与えてあげてください。
遊びが深まればコミュニケーションも高度に
遊びが深まると、コミュニケーションの内容も高度になっていきます。
ルールを決めたり相談をしたり。
相手と折り合いをつける機会が生まれたり、もめごとも生まれたり。
こういった機会はすべて発達に必要なハードルです。
そういった意味では、遊びの深さは3つの要素の中でも特に重要になってきます。
スパーク西京極では、1人のお子様に療育スタッフが1人以上付き、遊びを通じてコミュニケーションの力を育んでいきます。
1人では乗り越えられないハードルも、信頼できるスタッフと一緒ならきっと乗り越えられます。
夏祭りを実施しました
今年は新型コロナウイルスの影響もあり、各地の大小さまざまなお祭りが中止となりました。
季節を感じるイベントは子どもの発達にも非常に大切。
なんとかならないものかと、スパーク西京極では3日間、人数を限定して夏祭り療育を行いました。
もちろん消毒やスタッフのマスク着用、人数の限定といった感染症対策を徹底したうえでの実施です。
飲食ブースに使った材料は8大アレルゲンの入っていないものを使用(事前聞き取りも実施)。
夏祭り療育の目的は大きく3つです。
1.親子やお友達、スパークでの夏の思い出作り
2.ブースで引換券を渡したり、順番を待ったりするなどの社会性を学ぶ
3.微細運動や体のコントロールを必要とするブースで運動療育(アートコーナーやストラックアウト)
かき氷も本格的でした。
わたあめの出来る過程に興味津々!
ヨーヨー釣りとアートコーナー(手形アート、新聞紙遊び)で微細運動も!
ストラックアウトでコントロール能力も楽しく鍛える!
事前の準備も楽しく!
子ども達に楽しんでもらえて、幸せで有意義な療育イベントになりました。
フィールドスパークに続いて今年2回目のイベントも無事終了しました。
皆さまありがとうございました!
遊びを通じて感覚を鍛えよう
発達に特性のある子どもたちには、「感覚特性」がある場合も少なくありません。
感覚特性とは、音や目から入る情報、触覚などに過剰な反応を示したり、鈍感だったりすることです。
例えば…
・車の音やドライヤーの音など特定の音が苦手
・人混みでパニックになりやすい
・痛みに対して鈍感
・触られることを非常に嫌がる
・繰り返しのジャンプや頭を振る行動
・姿勢を保っていられない など
感覚特性についてはまだ理解されていないことも多いそうですが、体が感じ取る様々な感覚を整理してまとめる「感覚統合」と深く関係していると考えられています。
今回は感覚について、
そして、感覚を統合していくにはどんな遊びをしていけば良いかを考えていきます。
人は様々な感覚を整理して生きている
私たち人間は、外からの刺激に対して複数の感覚情報を得て、脳で必要な情報を整理をして生きています。
ところが、この整理が上手くいかないと上述したようなトラブルにつながることがあります。
【感覚の種類】
①五感(触覚、聴覚、視覚、嗅覚、味覚)
②固有受容感覚(筋肉や関節の動きを感じとる感覚)
③前庭感覚(バランスを取る、スピードを感じる等)
絶えず入ってくるこれらの情報の整理や取捨選択をしているのが感覚統合です。
感覚が統合されることで、自分の体を適切に使いこなすことができたり、他者とのコミュニケーションを上手くとれたり、目の前の作業に集中することができたりします。
今このブログを読んでくださっている皆さんは、画面から入ってくる視覚に集中しているはず。
しかも、画面にある余計な場所(時間の表示や充電の表示)ではなく、文字に対して注意を向けています。
余計なものも視覚として入ってきていますが、そちらに注意を向けていません。
外から音が聞こえてきますが、BGM程度のもので、今は文字に集中しているので気になりません。
人と話すときも、その人を見るという視覚、声を聴くという聴覚に集中しています。
ところが、感覚が統合されていないと目に入るものすべてが同じくらいの重要度で見えたり、
聞こえる音がすべて同じ大きさで聞こえたり、
会話中に視覚や聴覚以外の他の感覚も同じくらい働いてしまって、コミュニケーションに集中できなくなったりします。
他にも、感覚統合が上手くいかないと、カクテルパーティー効果と言われる「騒がしい場所でも必要な情報だけを聞き取れる能力」が未熟だったりします。
人混みを歩いていて、全部同じ音量で音が入ってくると「うるさーーい!ムリー!」ってなりますよね。
運動面では、視覚と固有受容感覚、前庭感覚が上手く合わないと、動きがぎこちなかったり、よくこけたりします。
子どもは様々な感覚を統合しながら発達していく
感覚は最初から完璧に統合されているわけではありません。
様々な経験を積む中で感覚刺激をたくさん受けて少しずつ統合されていきます。
発達に特性がある子たちは、このスピードがゆっくりだったり、特定の刺激への反応が強すぎて統合が上手くいかなかったりします。
感覚統合を進めるには、作業療法士(OT)さんによる感覚統合療法を受けてたり医療機関に相談するといった支援が効果的です。
それだけでなく、遊びを通じてたくさんの感覚刺激に触れる機会を作るということも効果的です。
たくさん遊んで感覚を刺激しよう(ご家庭でも出来る遊び)
感覚を統合していくうえで、まず基礎となるのは
触覚、固有受容感覚、前庭感覚、視覚と聴覚です。
遊びはこれらの感覚を自然と刺激してくれます。
◇ボールの投げあいっこ
目でボールを追いかけることで視覚を刺激し、コントロールしようとすることで固有受容感覚を刺激できます。
ボール投げでは重心の移動や全身の連鎖も学んでいくことが出来ます。
◇不安定な場所へ乗る
手を繋いでバランスボールやバランスディスク、くるくると回る勉強イスに座ったり乗ったりして回してあげる、様々なポーズを取ってみるなどは前庭感覚や固有受容感覚、視覚に刺激を与えることが出来ます。
四つ這いやうつぶせになったお父さんやお母さんの上に乗ってみることなども効果的。
他にも公園のグラグラする遊具(ブランコやシーソー)で遊んでみることもおすすめです。
◇ジャンプ
目的を持ったジャンプは固有受容感覚の刺激に効果的です。
線まで幅跳びをしてみたり、縄を飛び越えてみたり、高い所をジャンプでタッチしてみたり。
◇転がる
バンザイの状態で転がったり、膝を抱えてころがったりといった遊びは前庭感覚や固有受容感覚に効果的です。
軸を感じることもできるので、体幹が弱い子にも効果的。
◇感触遊び
粘土やスライム、手に絵の具を付けて絵を描く、手形を付けるなどの遊びは触覚を刺激します。
また、微細な運動のコントロールにも効果的です。
強制はしないで、楽しんで行う
こういった遊びは効果的ですが、強制する必要はありません。
お子様自身が「楽しい」と感じて、継続できることが大切です。
スパーク運動療育西京極スタジオでも、「楽しい」という感情を大切にしながら様々な遊びを療育スタッフと一緒に行います。
子どもたちの感情を育む中で、感覚統合につながる遊びにもたくさん取り組んでもらえればなと考えています。
【療育の様子】仮面ライダーでお友達とのやりとりを学ぶ
スパーク西京極では、他者とのやりとりをする練習も大切にしています。
子ども同士の遊びのシーンでよくあるやりとりを療育士が再現することがあります。
「これはどうやるのかなぁ?」
「僕もやりたい!」
「私もほしい!」
「こっちがいい!」
「ずるいよー!」
そんなやりとりを信頼できる療育士と繰り返すことで、子どもたちは他者と関わり、遊ぶ術を学んでいきます。
この日は仮面ライダーと戦隊ヒーローのラミネートをどう分け合うか相談中…
まずはじゃんけんで分け合ってみたけど…
そっちの方が強いー!
私2枚しかないー!
変えようよー!
どうしたらいいんだろう
そうだ、交換しよう!同じ数にしてみよう!
このような感じのやり取りが繰り広げられておりました。
遊びとして綺麗にまとまることも大切かもしれませんが、
「どうしたらいいんだろう」
「こうしてみよう」
「僕もこうしたいけど、お友達もしたいみたい」
そういったやり取りをたくさんすることは、もっと大切。
繰り返していくうちに、コミュニケーションを取って遊ぶ楽しさや、他者と分けあう良さなどを知っていきます。
最後は壁に集結させておしまい!
施設全体の除菌・抗菌作業をしていただきました
先日、スパーク西京極の施設全体の除菌・抗菌作業をしていただきました。
光触媒という技術を駆使した除菌・抗菌技術で、効果は約1年程度持続するそうです。
子どもたちに安心して遊んでいただくべく、最善を尽くしております。
療育室はもちろん、トイレ、事務室、スタッフのパソコンや備品まですべて除菌・抗菌をしていただきました!


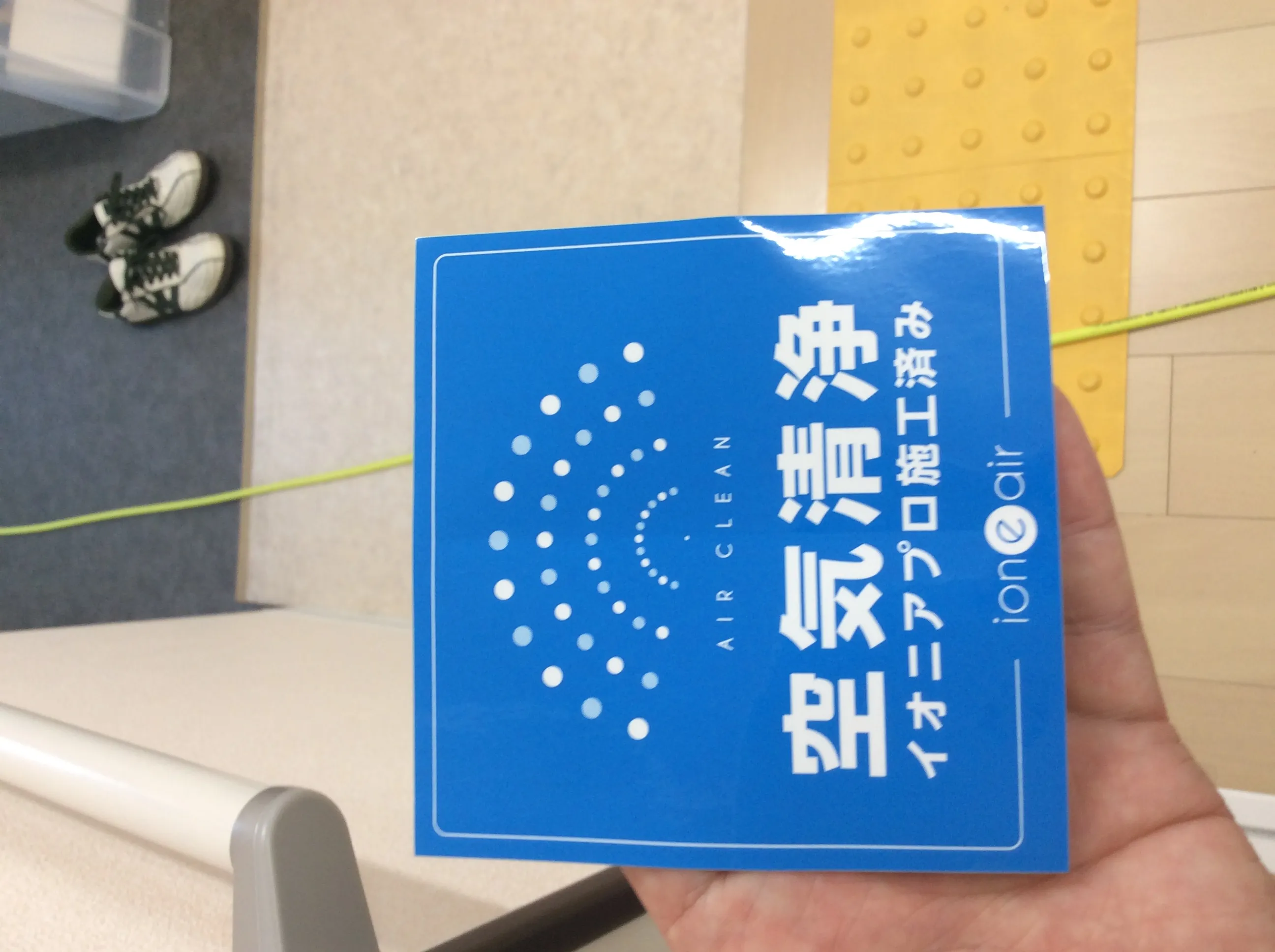

スパークでたくさん褒めたり大きなリアクションを取る理由
スパーク運動療育では、、スタッフが大きなリアクションを取りながら子どもをたくさん褒めて、体を使った遊びをしています。
それにはちゃんとした理由があります。
発達に特性のある子どもたちは、脳機能に先天的な特徴があると言われています。
どこか特定の脳の神経のつながり(配線)が強かったり弱かったりしていると考えられています。
脳はとても変化に柔軟な性質を持っているため、適切なアプローチをすればこういった配線を繋ぎ変える、もしくは新しく構築することが出来ます。
私たちが外からの刺激に対して何らかの「行動」をとるには段階があります。
1.感覚として入った情報(見た、聞いた、思ったなど)を処理
2.その情報に対して感情が生まれる(やりたい、おもしろそうなど)
3.過去の記憶や今の気持ちなどを総合して、判断を下す(やってみよう、やめておこうなど)
4.言葉や行動としてアウトプットする
5.記憶として定着していく
発達に特性がある子たちは、まず②の感情の段階に対してのつながりに個性があると考えています。
感情は行動の根っこになる部分であり、感情が育っていくことこそが脳が発達していくカギになると言えます。
「感情」がしっかりしてくるからこそ、考えたり行動したりすることが出来るからです。
「感情の段階に個性がある」と言っても様々なパターンがあります。
刺激に対して感情が薄い子もいれば、自分で感情のコントロールが上手くできない子まで様々です。
いずれにせよ、感情を豊かにしてあげるような関わり、感情を調整できるようになる関わりが必要です。
そこでスパーク運動療育では特徴的な2つの関わり方をしています。
1.大げさなリアクションを取る
2.褒める
大げさなリアクションを取るとは、感覚として入ってくる刺激が豊かになる(強さや種類)ということ。
そうすることで、「楽しい」「おもしろい」といった子どもたちの感情が大きく働きやすくなります。
それを繰り返す内に少しずつ子どもたちの感情も豊かになっていきます。
スパークでは療育の時間中に褒めるということをたくさん行っています。
何かできたことだけでなく、ちょっとした行動から何気ない偶然の行動までとことん褒めます。
褒める、すなわち共感や承認をされることで子どもたちの感情をぐんぐん引っ張ります。
他者から認められるということは、自己肯定感の高まりやストレスの軽減にもつながります。
感情を育てるための下地作りとしても褒めるということは非常に大切になってきます。
問題行動の裏にある理由と気持ちを考える
発達に課題のある子どもたちは、「問題行動」をしてしまうことがあります。
問題行動の代表的なものには、つねる、噛むなどがあります。
こういった行動に対して、ただ禁止してしまうという対処を取りがちです。
しかし、スパーク運動療育では「問題行動」が出てしまう理由や気持ちを考えるようにしています。
例えば、つねるという行動にも子ども1人1人、場面によって理由が異なります。
◇何か気に入らないことがあった
◇びっくりしたり、嫌な気持ちになったりした
◇関わってほしい(関わる手段が分からない)
などなど
そして、ただその行動を禁止するだけでなく、社会性を育むための関わり方をしています。
①痛いという事実を伝える
療育士が「痛い」という感情をしっかりと表現し、「強くつねると痛い」という事実を伝えます。
それを繰り返し経験することで、子どもたちはつねることは痛いことで、他者も自分も嬉しくないことだと学んでいきます。
②気持ちを代弁する
問題行動には理由があります。
嫌なことがあってつねっているのであれば「嫌だったね」と子どもの気持ちを代弁し、気持ちを表現するお手本を示しています。
このように、スパークでは問題行動をやめさせるのではなく、問題行動が出てしまう時の子どもの気持ちを考え、共感し、関わり方を示すことを何度も繰り返す内に、少しずつ子どもたちは気持ちを表現する術を学んでいきます。
行動はすぐに改善するわけではなく、粘り強い関わりが必要です。
スパーク西京極では、子どもの気持ちに寄り添いながら気長に関わっていきます!
ご家庭ではなかなか難しい関わり方かもしれませんが、少し気持ちに余裕があるときに、問題行動の理由や気持ちについて考えてみてください。
